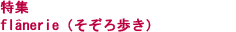特集: flânerie(そぞろ歩き)
伊豆半島ジオパーク:城ケ崎海岸(静岡県・伊東市)
城ケ崎海岸は、約4000年前に起きた大室山の噴火で流れ出した溶岩が海の一部を埋め立て、さらに海の侵食作用で削られてできた
雄大な溶岩岩石海岸です。
門脇埼では、城ヶ崎のダイナミックな地形を手軽に楽しむことができます。
さらに門脇灯台にのぼれば、海岸の雄大な景観と城ヶ崎を作った大室山を一望できます。
起伏に富んだ海岸線にかかるつり橋からは、溶岩が冷えて収縮する際にできる柱のような形をした岩「柱状節理」も観察できます。
溶岩の表面は赤みを帯びたぎざぎざした岩で覆われています。これは、溶岩が流れる際に先に冷え固まった表面の「殻」が、
後から流れてきた溶岩に砕かれてできたもので、「クリンカー」と呼ばれる構造だそうです。
赤みを帯びているのは空気に触れていた溶岩の表面部分が酸化して酸化鉄ができたためです。
。
海岸線は絶壁や岩礁が連なり壮観!

特に門脇崎の海の吊り橋は長さ48m、高さ23mで深い海蝕洞を上から眺めることができスリル満点です。

絶壁の上には荒海に糸を垂れる釣り人がまるで、広重の浮世絵にあるような構図でたたずんでいます。

つり橋の先には展望台付きの門脇灯台があり螺旋階段を上っていくと展望台から変化に富んだ溶岩磯の景観を楽しむことができます。
この辺り一帯は、2012年に伊豆半島ジオパークの東伊豆エリアとして日本ジオパークに認定されています。
【DATA】
伊豆半島ジオパーク
https://izugeopark.org/